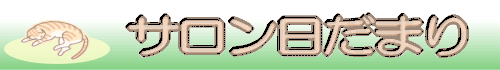
令和6年(2024)年度の活動
令和4(2022)年度の活動 令和5(2023)年度の活動
令和2(2020)年度の活動 令和3(2021)年度の活動
平成30(2018)年度の活動 令和元年(2019)年度の活動
平成28(2016)年度の活動 平成29(2017)年度の活動
平成26(2014)年度の活動 平成27(2015)年度の活動
平成24(2012)年度の活動 平成25(2013)年度の活動
平成23(2011)年度の活動 平成22(2010)年度の活動
平成21(2009)年度の活動 平成20(2008)年度の活動
平成19(2007)年度の活動 サロン"日だまり" 開始から1年の歩み
写真をクリックすると大きくなります
第181回 令和6年4月16日(火) 参加者14名
「NHK放送博物館見学と愛宕神社参拝」
4月16日(火)陽春の好天気の朝、14名の皆さんが、東京メトロ日比谷線の「神谷町駅」 改札口に集まりました。 改札口に集まりました。
我が国では米国から5年遅れて1925年にラジオ放送が開始されました。来年は放送開始100年を迎えます。このタイミングで「日本の放送の歴史を勉強する」のも意義深いことと思い、NHK放送博物館の見学を企画しました。
「NHK放送博物館」は1956年(昭和31年)にNHK発祥の地である愛宕山に造られました。
ラジオからテレビ放送へ、初めはモノクロ(1953)、それからカラー(1960)へ、更に衛星中継放送(1963)やハイビジョン(1990)への進化を経て、現在は超高精細デジタル放送へと進化しています。私たちにとって最新技術も面白いのですが、それ以上に私たちが生き抜いた 昭和時代の放送の歴史は懐かしさに感動してしまいました。 昭和時代の放送の歴史は懐かしさに感動してしまいました。
ラジオでは、二重の扉(1947~1960)、トンチ教室(1949~1968)、私は誰でしょう(1949~1969)、そしてテレビでは、ジェスチャー(1953~1968)、私の秘密(1955~1965)、夢で逢いましょう(1961~1966)など、アナウンサーだけでなく出演者の顔を見て皆さん懐かしさがこみ上げたようです。また、昭和の皇太子殿下ご成婚の放映(1957)、東京オリンピック(1964)、読売ジャイアンツの9連覇(1965~1073)、MLBのパイオニアとしての野茂英雄の活躍(1995~2008)など、当時のままの映像を楽しむことができました。
 NHK放送博物館の後は歩いて2分の至近距離にある愛宕神社に参拝しました。愛宕神社は1603年、徳川家康の命により、防火の神様として創建されました。配祀は日本武尊(やまとたけるのみこと)です。 NHK放送博物館の後は歩いて2分の至近距離にある愛宕神社に参拝しました。愛宕神社は1603年、徳川家康の命により、防火の神様として創建されました。配祀は日本武尊(やまとたけるのみこと)です。
愛宕山(25.7m)は東京23区内での最高峰です。その頂に立てば、江戸時代は江戸の街並みと東京湾を一望できたと言います。3代将軍・家光の時代に86段の急な石段を馬で駆け上がった曲垣平九郎の逸話は有名です。「出世石段」と言われる所以です。
春の盛りのせいか、結構大勢の参拝者がいて、私たちは列の後方に並んで、順番を待ちま した。皆さん、それぞれの願い事をお祈りしました。 した。皆さん、それぞれの願い事をお祈りしました。
アフターは神谷町駅近くの町中華「隆盛園」でワイワイガヤガヤと楽しい時間を過ごしました。
お腹いっぱいの中華料理とビールやワイン、日本酒などをいただき、懐かしい昭和の話題を楽しんで、午後2時45分にお開きとなりました。詳しくは写真集をご覧ください。(喜田・記)
第180回 令和6年3月19日(火) 参加者17名
「昭和館の見学」
 今月は九段にある昭和館の見学です。 今月は九段にある昭和館の見学です。
11時、九段下駅に17名の方が参加されました。靖国神社、武道館などの最寄り駅で4番出口をでると目の前に昭和館があり便利な場所でした。
ここは戦中・戦後の生活にかかる資料を展示して、人びとのくらしや戦争にまつわる行動など、当時のことを次世代に伝えるための施設で、平成11年に開館しました。
 常設展の入口は7階からでした。入ると昭和10年~20年終戦までの資料があり、ブース毎に当時の一般的(?)な家庭で使用されていたもの、統制のもと自粛自省のくらし、子供たちのおかれた環境、空襲に関する資料などがありました。 常設展の入口は7階からでした。入ると昭和10年~20年終戦までの資料があり、ブース毎に当時の一般的(?)な家庭で使用されていたもの、統制のもと自粛自省のくらし、子供たちのおかれた環境、空襲に関する資料などがありました。
皆さん当時を思い出し会話が弾んでいました。
階段を降り常設展の6階には20年~30年頃の資料が置かれていて、戦後の物不足の中での厳しい生活、その後の教 育環境の復興に関する資料などがあり、徐々に社会全般が生活再建、産業復興に向けて明るい兆しを見せ始めたということです。 育環境の復興に関する資料などがあり、徐々に社会全般が生活再建、産業復興に向けて明るい兆しを見せ始めたということです。
まるでブギウギのリズムに乗って、人々の顔に明るさが増えてきたような感じがしました。
3階には超特急と呼ばれた「つばめ」に関する資料などがありました。東京~神戸間を9時間ということで早かったのでしょう。今は新幹線で3時間弱、時代および技術の変化を感じます。およそ1時間の見学でした。

昭和館で集合写真を撮り次は楽しみな食事です。
飯田橋まで東京大神宮の前を通って20分ほど歩きました。食事はコース料理飲み物付でほろ酔い、2時半に解散しました。
第179回 令和6年2月21日(水) 参加者12名
「日本科学未来館の見学」
前日の初夏のような暑さが嘘のように冷たい雨が降る寒い日でしたが、参加予定者12名はゆりかもめ東京国際クルーズターミナル駅に全員時間前に集まり、約10分歩いて日本 科学未来館(未来館)に行きました。 科学未来館(未来館)に行きました。
未来館は2001年(平成13年)に開館し、宇宙飛行士の毛利衛が2021年(令和3年)まで初代館長を務められた博物館で、丁寧に見学すると一日以上掛かると言われています。
従って、今回は 昨年11月に常設展が①老い②地球環境③ロボットをテーマにリニューアルされましたので、常設展を中心に見学しました。
 まず 3階の①未来をつくるでは *ハロ!ロボットコーナーと*老いパークコーナーを見ました。ロボットコーナーには人とのコミュニケーションやセラピーを目的に開発されたロボット①ラボット(対話型)②アイボ(エンタテインメントロボット)③パロ(心をケアーするセラピーロボット)など展示されておりロボットとの触れ合いを楽しむことができました。 まず 3階の①未来をつくるでは *ハロ!ロボットコーナーと*老いパークコーナーを見ました。ロボットコーナーには人とのコミュニケーションやセラピーを目的に開発されたロボット①ラボット(対話型)②アイボ(エンタテインメントロボット)③パロ(心をケアーするセラピーロボット)など展示されておりロボットとの触れ合いを楽しむことができました。
また、老いのコーナーでは①耳の状態を確認する装置があり「サトウ」「アトウ」「カトウ」を聞き分けられるかの検査②将来老顔になった時の自分の写真を撮ったりすることができる装置などがあり、「老い」るとはどういうことかということと、自分はどの程度「老い」ているか各自自由に試して楽しみました。
 次に5階の②地球を探るー地球環境コーナーではフィジーを例に地球温暖化により海面が上昇して、お墓が水中に没したり、満潮時に海辺の家の床上に海水が上がり、住めなくなったりした状況を見せて、人類が揃って地球温暖化防止に努めなければならないことを訴えていました。 次に5階の②地球を探るー地球環境コーナーではフィジーを例に地球温暖化により海面が上昇して、お墓が水中に没したり、満潮時に海辺の家の床上に海水が上がり、住めなくなったりした状況を見せて、人類が揃って地球温暖化防止に努めなければならないことを訴えていました。
日本でも地球温暖化の影響を少なからず受けていますが、フィジーのように生活の根底を揺るがすまでには至っていないので、それほど深刻には取り組まれていないように感じていました。これからの我々が取り組まなければならない大きな課題だと感じる展示でした。
 約1時間半見学した後ゆりかもめに乗って新橋に戻り銀座ライオン新橋店でいつものアフターを楽しみお開きとしました。 約1時間半見学した後ゆりかもめに乗って新橋に戻り銀座ライオン新橋店でいつものアフターを楽しみお開きとしました。
帰りには未来館のお土産「JAXA」の帽子をかぶった人が二人いました。
2024.2.22 芦川記
第178回 令和6年1月16日(火) 参加者20名
「明治神宮初詣」
2024年は元日の「令和6年能登半島地震」、2日に「日本航空機と海保機の衝突事件」という痛ましい災害と事故で幕開けしました。しかし、今年1年を通してそのような悪い年になるはずはありません。
今年は恒例の初詣を「明治神宮」に参りました。明治神宮はご存知かもしれませんが、明治天皇と昭憲皇太后を祀っています。創立は大正3年(1914年)11月です。70万平米の土地に全国から10万本の木が集められ、11万人のボランティアによって植栽して作られた人工林です。土地は江戸初期は加藤家(加藤清正)の下屋敷でした。江戸中期に井伊家の下屋敷になったところです。
 以下、報告します。 以下、報告します。
1月16日(火)午前11時、明治神宮入口の神宮橋の袂に20名が集合しました。
皆、清々しい気持ちで大鳥居から参道を本殿に向かいました。途中、明治天皇御製と昭憲皇太后御歌の掲示の前で全員で記念写真を撮りました。
その後、全員が揃って本殿に参拝しました。1年の安寧をお祈りしました。
 参拝の後は、それぞれ思い思いに静かな明治神宮の森を散策しました。私は苑内にあるお洒落なCaféのウッドデッキで日向ぼっこをしながら、森を渡る風の音を聴きながら暖かいコーヒーを頂きながら皆が集まるのを待ました。 眠くなるような素敵な時間でした。小鳥の声、森の風、近くを走るJR山手線の電車の音、子供の声、いろんな音が聞こえてくるのを発見しました。 参拝の後は、それぞれ思い思いに静かな明治神宮の森を散策しました。私は苑内にあるお洒落なCaféのウッドデッキで日向ぼっこをしながら、森を渡る風の音を聴きながら暖かいコーヒーを頂きながら皆が集まるのを待ました。 眠くなるような素敵な時間でした。小鳥の声、森の風、近くを走るJR山手線の電車の音、子供の声、いろんな音が聞こえてくるのを発見しました。
12時30分全員が集合して、いざアフターへ。
 アフターは電車で2つ目の駅「恵比寿」の駅ビル6階にある「銀座ライオン」(恵比寿店)です。午後1時から2時間、それは楽しいアフターの時間です。 アフターは電車で2つ目の駅「恵比寿」の駅ビル6階にある「銀座ライオン」(恵比寿店)です。午後1時から2時間、それは楽しいアフターの時間です。
どうぞ、写真集をご覧ください。午後3時に満ち足りた顔で散会しました。
(喜田祐三・記)
|

